研究概要
    
<はじめに>
卒業論文や修士論文のテーマの決め方は、特に講座・分野・指導教官を決めようとしている学生さんにとっては最大の関心事でしょう。当然、本研究室でも多くの要素を考慮します。我々の関連した研究分野では、テーマを決めること自体がその研究の半分近くのウェイトを占めます。研究テーマが決まるということは、その研究の意義付け・アプローチの手段・結果の最低限の予測とその意義、が明確になるということです。ですから、そう簡単なことではありませんし、これから卒論を始めようという3年生が易々とできることではありません。普通、指導教員の直接的なアドバイス無しにこれができるようになるのは、博士課程に入ってから(早くて!)だと思います。実は博士の学位を持っていても、それができないという人は少なくありません。
所属する研究グループを決めることと、直接的な指導教官を決めることは、密接に関係していますが、微妙に異なることも事実です。最初から指導教官を決めてしまうのもよし、まず研究グループを選んでから、具体的なテーマに従って主な指導教員を決めてもよいでしょう。例えばお隣の地質教室では、教員がいくつか卒論テーマを提示してそれを選ぶ形式だと聞いています。ただしこの場合も、テーマが抽象的であれば、まずおおよその研究分野を選ぶのと同じことになるのでしょう。さて、地球惑星物質科学科の場合には“分野と呼ばれる研究ブループ(鉱物・岩石・資源環境・物性・岩石地質・島弧という、あれ)が存在し、このホームページがそうであるように、分野単位で物事が動くことが多いのは事実です。しかし、分野内部での研究や教育に関する結びつきの強さは様々です。教員一人一人が基本単位の大講座制に近い実態のブループもありますし、強力な教授の下、いわゆる小講座制に近い体制を敷いているグループもあります(ちなみに、正式には地球物質科学講座という大講座で、分野は運用上のものです)。 いずれにも一長一短があり、一概にどちらが良いとは言えません。例年の3年生は、このような、研究グループの体制や学生などが総合的に創り出す雰囲気・研究室のカラーをかなり考慮しているようです。院生などからの情報、教員からの情報、を合わせて、自分の目を持ってください。
学科内部の学生さんにはなかなかわからないかもしれませんが、当学科は、非常に狭い学問分野に多くの教員が存在しています。これだけ集中している教室は、全国的に見ても非常に珍しいかもしれません。その結果、分野間で研究対象や研究手法の重なりも大きくなっていますから、3年生には、どのお店に入ったら良いのか、場合によってはとても迷うかも知れないと思います。もっと違いが判り易いような看板を掛けて欲しいと思うかもしれません。けれども、狭い学問範囲の中で無理に差別化をしようとするとロクなことは無いので、ちょっと我慢してください。我々がどのような指導方針を持ち、本研究室でどのような基礎的学力・研究能力が身につくのか、どのような方向に研究を発展させられるかを十分に理解して判断して頂きたいと思います。修士・博士への進学時等に、本人の意志で他研究室・他大学へ移動することは構いませんし、もちろん基礎学力のある外部の方の編入も歓迎します。
過去4年間の例では、島弧マグマ学分野への所属が決定すると、すぐに続いて卒論のテーマ作りを開始します。このあとは、卒論(・修論)テーマの決め方についての中村の考えを説明します。
 <三つの質問>
<三つの質問>
どの研究室でもそうだと思いますが、我々の分野でも、学生さんと繰り返しよく相談して決めていきます。早い人はすぐに決まりますし、4年生の夏まで決まらなかった例もあります。テーマの相談の仕方は、いつもお決まりのやり取りから始まります。『院に進学しますか?』 『どんなことを研究したいですか?』 『どんな講義や実習を面白いと思いましたか?』
最初の質問
学部卒で就職するのか、修士課程に進学するのかは、かなり重要な要素です。「まだわからない」という答えももちろんアリです。絶対に就職するという意志が固まっている場合だけ、この点を考慮します。その場合には、1年間でまとまり易いという要素を考慮します。他大学の院に進学を希望する場合も、ほぼ同様です。
ここでいう“まとまる”というのは、“まとまった結果”が出る、という意味ではありません。偏った作業にだけ時間をとられるのではなく、ある程度、多様な仕事を経験して、ひとまとまりの仕事として他の人に発表し、論文として書き上げることができる、という意味です。それによって、きっと社会に出てからも役立つであろう素養、大学4年間の間に獲得していることが期待されているであろう素養を、身につけてもらうことができると思うからです。私は、修論までは、失敗や迷走で終わっても一向に構わないと思っています。他大学のある研究室では、卒論では、まず絶対に成功しないテーマを与える、という話を聞いたことがあります。研究では、「失敗によって得られることは成功によって得ることよりもずっと多い」からでしょう。 なお「進学するかわからない」という人には、仮にそのまま進学しても構わないよう、進学希望者と同様のテーマを考えます。
修士の先、博士に進学を希望するかどうかは、尋ねるかもしれませんが、どのような答えを貰っても、実はあまり本気にはしません。「進学する」と言われても、しばしば気が変わるものですし、進学させられるかどうか(適性があるかどうか)も学部の段階ではわかりません。逆に、「絶対に行かない」と言われても、「ひょっとしたら途中で気が変るかもしれない」と思いつつ、つきあいます。何故?私自身がそうでしたから。
私は、重要な問題、大きな問題に取り組むことが、ともかく重要だと思っています。これは、極端な放任主義であった私の指導教官の、ほとんど唯一の指導であり、私には在学中はその意味がよくわからず、助手になって数年してからようやく、浸み込むように、わかった(つもりの)ことです。ですから、修士に進学する人には差別無く、私が重要だと思うテーマを全力で考えます。修士で就職すると表明したからといって、矮小なテーマを与えるようなことはありません。重要な(しばしば困難な)テーマを考えますから、心配しないでください。でも、その分覚悟してください。日々を無難に過ごしたい安定志向の人は、私を指導教員に選ばない方が良いでしょう。なお、ついでに言えば、それまでの成績の良し悪しは全く関係ありません。その後の努力次第で挽回する余地は十分あります。
二つ目の質問
『やりたいこと』について。これは実に、学生さんによって人それぞれです。レストランで注文をするとき、具体的なメニューにワインまで指定する客から、ただ、『和食が食べたい』とか『魚料理が好き』とかいう客までいるようなものです。それどころか、大学では、空想上の料理を注文したり、中には、ただ『腹が
減った』とだけしか言わないに等しいお客も居ます。やれやれ。
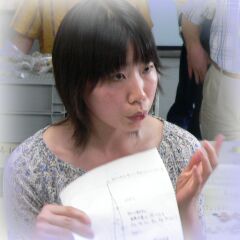 具体的なメニューを指定されたからといっても、その料理(=テーマ)を出せるかどうかわかりませんし、仮に出せたとしてもその通りの料理を出すとは、限りません。最近では、大学も客商売と心得よ、と言わんばかりの風潮ですが、この点では私は注文の多いレストランであるかもしれません。いろいろな話をしながら、その学生さんが本当に興味を持っているのはどこか、地球科学のどういう点に興味があるのか、自然科学のどのようなスタイルが好きなのか、といった、興味の中心の在り処を私なりに捜し当てて、それに最も近いであろうテーマがあれば、それを提示します。 研究の世界は、短所を補う勉強をするよりも先に、まず長所を伸ばすところだと私は思っています。研究を続けていく上で、前者は必要条件、後者は十分条件に相当します。どちらも大切ですが、後者が伸びれば自然と前者にも意識が向くものです。問題意識をもってから、立ち戻って行う勉強は、目的がはっきりせずに行う勉強の何倍も能率が良いものです。三番目の質問も、その学生さんの得意意識を引き出し、自覚してもらうためのものです。
具体的なメニューを指定されたからといっても、その料理(=テーマ)を出せるかどうかわかりませんし、仮に出せたとしてもその通りの料理を出すとは、限りません。最近では、大学も客商売と心得よ、と言わんばかりの風潮ですが、この点では私は注文の多いレストランであるかもしれません。いろいろな話をしながら、その学生さんが本当に興味を持っているのはどこか、地球科学のどういう点に興味があるのか、自然科学のどのようなスタイルが好きなのか、といった、興味の中心の在り処を私なりに捜し当てて、それに最も近いであろうテーマがあれば、それを提示します。 研究の世界は、短所を補う勉強をするよりも先に、まず長所を伸ばすところだと私は思っています。研究を続けていく上で、前者は必要条件、後者は十分条件に相当します。どちらも大切ですが、後者が伸びれば自然と前者にも意識が向くものです。問題意識をもってから、立ち戻って行う勉強は、目的がはっきりせずに行う勉強の何倍も能率が良いものです。三番目の質問も、その学生さんの得意意識を引き出し、自覚してもらうためのものです。
このように、たとえ卒論であっても、研究テーマを設定するのは簡単なことではありません。普段からなるべく幅広い範囲の勉強をし、頭の中で問題意識が有機的に結合・発展するように心掛けているつもりですが、暖めているアイデアは無数というわけではありません。、もし我々で適当なテーマが出せないような場合には、はっきりと他の研究室を勧めます。
<対象と手法>
もう少し具体的に、テーマの決め方について話しましょう。研究には、対象と手法の二つの要素があります。ちょうど、織物の縦糸と横糸のようなものです。学生さんが、どのような対象に興味があり、どのような手法が向いているのか(いないのか)、を考慮します。これをすぐに見定められない場合には、話の中から出てきたキーワードに関連した教科書や論文を手渡して、読んでもらいます。その上で、どのような点に興味を持ったか(持たなかったか)を、尋ねます。また、仮のフィールドや実験テーマを決めて作業を始めてみて、そこから学生さんが何を考えどう反応したかを見たりします。実は大学院に進学する人の場合、卒論を丸々このステップに費やすことも珍しくありません。その場合には、修論からパッとテーマを変えることになりますが、こうすると良い結果が出る場合が多いようです。まさに、“急がば回れ”、そのものだといえるでしょう。
 <フィールドワークについて>
<フィールドワークについて>
20年くらい昔には、地学関係の大抵の大学では、卒論はフィールドワークと相場が決まっていたものです。たとえば火成岩岩石学関係であれば、まず地質図を書き、岩石薄片を作って偏光顕微鏡で記載し、全岩化学組成をXRFで、鉱物化学組成をEPMAで分析し、結晶分化作用などマグマ組成のバリエーションの説明を考えて、そのあとは必要に応じて同位体を測ったり実験をしたりモデリングして、地域地質から、より一般的な問題へと拡張してゆく、そういう“型”が存在しました。
当時、この方式には、数多くのメリットや必要性がありました。まず、ありのままの自然を自分のペースでよく観察できます。基礎的なことを、体系的に勉強することができます。ルーチンな作業をしている間に学生は自分の頭でよく考える時間があります。自分の興味がどこにあるのか、何が得意で何か不足しているのか、といったことを、自覚することができます。こうして、うまくすれば、フィールドから自分でテーマを見つける力をつけることができます。また、そのフィールドの地質層序や岩石組成がまだ知られていなければ、仮に際立った発見が無かったとしても、国内の雑誌に結果を論文として発表することができます。フィールドワークはある種の特殊技能なので、身につけていれば、民間の関連分野に手堅く就職することができました。また多くの地学系の大学では、教官公募の要件にフィールドの指導を加えていました。さらに、これはあとでわかったことですが、教官は最初にちょっとだけフィールドの指導をするだけで、それ以降は指導に手間も費用もあまりかかりません。その分、学生の旅費や道具代の負担は相当なものですけれど。
 現在でもなお、卒論でフィールドワークを行う場合、此処に述べた多くのメリットは健在です。ですから、学生さんがフィールドワークを積極的に希望する場合には、それを尊重しますし、研究対象によってはフィールドワークから入ることを薦める場合もあります。
現在でもなお、卒論でフィールドワークを行う場合、此処に述べた多くのメリットは健在です。ですから、学生さんがフィールドワークを積極的に希望する場合には、それを尊重しますし、研究対象によってはフィールドワークから入ることを薦める場合もあります。
しかし、現在では当時とは学問の大局的な状況が大きく変化しています。たとえば、火山であれば全く人の手が入っていない火山はとても少なくなりましたし、そもそも地球浅部でのテクトニクスの枠組が決定した現在、あえてそのような辺地を探し出す意義は薄いでしょう。マグマや岩石の化学組成の多様性を説明するという意味での岩石学はほぼ終わって(“落ち穂”というのは常にあるものですけれど)、“型”通りの仕事では“食えなく”なっています。実は、“型”の有無は、大学や大学院における指導方法と密接に関係があります。先ほど私の指導教官は極端な放任主義だったと書きましたが、それでも学生が「なんとかなった」のは、別に我々が優秀だったからではなく、この“型”があったからに他なりません。先輩がやることを、フィールドだけを変えて真似していれば、修士までは特に問題なく修了できたのです。壮年期の学問分野には、必ず、この“型”が存在するものです。別な言い方をすれば、“型”無しには多人数の学生を“さばく”ことはできません。現在、我々は新たな“型”を模索しつつ悪戦苦闘しているところです。学生の指導の効率はとても悪くて辛いものがありますが、学問が世代がわりしつつある証拠でもあり、ある意味では面白い時代なのかもしれません。
<帰納と演繹>
フィールドワークや、それに基づく研究では、自然の観察結果を帰納的に統合し、内部矛盾の無いストーリーを組み上げていくことになります。このような帰納的な研究スタイルは、まず初めに作業仮説(モデル)を立ててから実験や数値シミュレーションを行い、ある前提・仮定の下に、こうなっているはずだ、という議論を行う演繹的な研究とは、自然に対するアプローチの方向としては対照的なものです。この両者は、ちょうどトンネルを山の両側から掘り進むようなものであると私は思っています。それぞれに、面白さも困難も存在します。前者のタイプの研究では、自然の複雑さを整理できず、普遍性のある結論を引き出せないことがしばしばあります。その一方で、正真正銘の自然(事実)を直接的に扱っているという確信を持てますし、想像すらしなかった発見ができる可能性もあります。ただし誰もがそのような発見に出会えるわけではありません。論理的な検討に最低限必要なデータセットが揃うまでは、あまり理屈をこねずにひたすら頑張るという「馬力」、そしてそのかわり、自分が自信を持って出したデータはたとえ1点でも徹底的に大切にする「正直さ」の両方が必要です。少し別の言葉で言い換えると、データの中に潜む発見を見逃さない「注意深さ」と、データに対する「誠実さ」、データが自ら真実を語り出すまで、根気良く論理の積み重ねとデータの追加を続ける「根気の良さ」ということになります。格好つけようとか、手早くまとめようといかいう邪心を持って予定調和的な研究(らしきもの)をしても、絶対に発見は得られません。それに加えて、多少の運も必要かもしれません。さて、特にねらいを定めずフィールドに入った場合、そこからしっかりとしたテーマを見つけられるようになる人は、東大・東工大・東北大のいずれでも、統計的に見てほぼ4人に一人くらいです。単に型どおりのデータを出し、お決まりの議論をするだけなら簡単ですけれど、もしbreak
throughを目指すのなら、このタイプの研究の道のりは非常に険しくなると思ってください。一方、演繹的な問題設定の上に始める研究は、位置付けが明確な分、目指している方向がわからなくなることは少なく、定型に納まってデータを出していくだけなら、技術面などで部分的な困難にぶつかることはあっても、根本的な危機に陥ることは比較的まれです。出てきた結果の意義は明確ですし、ストーリーが閉じずに困るということもありません。けれども、ひとたびオリジナリティのある重要な仕事をしようと思ったら、よく考えて他人とは違う実験手法を考案しないといけませんし、思うように結果が出ないことがむしろ普通です。裏を返せば、実験であっても、思いもよらない結果が出るということはよくあることです。結局、どのようなアプローチをとっても、新しい発見をしようと思えば、相応の産みの苦しみは伴うことになります。
フィールドワークから入って、自分の問題意識を持った時点で演繹的なアプローチに乗り換えるというやり方も、一定の成功を収めています。4年生の最初からねらいを絞り込んだ実験を始めても、その意味を学生さんが自分なりに咀嚼するのにやはり1年近くかかることが多いようですから、急がば回れということかもしれません。しかし、修士までの仕事をpublishしようとしたときには、卒論からテーマを継続したほうが時間的に有利であることは言うまでもありません。最近は学術振興会の特別研究員などに応募しようとする場合など、早い段階から論文を書き始めないと生き残れない時代になっていますので、どちらが良いかは結局は個々人に合わせて判断するしかありません。
先ほど、20年くらい昔にはフィールドの卒論には多くのメリットや必要性があった、と書きました。それは正しいのですが、今になって振りかえると、あまりに画一的に過ぎたかもしれません。海外での研究生活が長い高名な日本人研究者の何人かが、次のような指摘をしています。『…仮想している過程をどのように実験系に組み込み、何をどのように観測すれば良いかということで困ってしまうのである。伝統的に観察と記載を主にして教育されている地球科学者は実験科学・理論科学的素養が貧弱である。多くの可能性を前にしておりながら、これを有効に駆使する術を知らないことに気づくのである。結局、既成の商品化された実験装置や分析装置を使って膨大なデータを蓄積するが、そこから得られる情報は、常に同じ範疇に属するものである…』(飯山敏道著『実験地球化学』)、『地球科学は天体物理学や生物学と同様に自然の秘密を解き明かそうという科学の1つであるが、いままでの(固体)地球科学はこのような近隣分野に比べて、やや見劣りがするものだった。それは、一方で多くの地質学的研究があまりにも記載的で、物理学・化学的原理にもとづいた定量科学から程遠かったこと、他方で多くの地球物理学的研究では地球が単に応用数学の対象になっているだけで、観測事実の背後にあるミクロな物理過程が問われることが稀であったことなどのためである。』(唐戸俊一郎著『レオロジーと地球科学』)。自らの経験に照らして、実に適確な指摘であると思います。この意味で、当時から、もっと多様な指導方法があっても良かったのではないかと思いますし、現在ではなおさらです。
一般に教育の議論においては、必要だからと言ってあれこれ追加をするのは簡単ですが、不要だと言って切り捨てるのは容易ではありません。本当に必要なものが何か、がわかっていないと、何を相対的に後回しにして良いかが見えないからです。ある種の分野では、地震波トモグラフィの原理や精度を正しく理解できることが、昔でいうところの、フィールドで露頭が観察できることに相当するようになっているようです。これは考えてみると、どのような種類の波で地球を観察するかの違いにすぎないとも言えるかもしれません。地球惑星科学にとって、自然を観察することの重要性は普遍的なものだと思いますが、その具体的な方法については、もはや学生の資質に合わせて柔軟に考えるべき時でしょう。フィ−ルドワークの必要性を過大に強調するのは、ブラインドタッチの時代に誰もがナイフで鉛筆を削れないといけない、と言うのにちょっと似ています。
若いうちからの豊富な経験と基礎的な修行が必要な研究手法は、別にフィールドワークに限ったことではありません。たとえば装置の開発から行うような実験家や、本格的な分析化学者は、時間に余裕のある学生時代に、旋盤を回したりビーカーを洗ったりしながら体で覚えないと育ちにくいものかもしれません。物質科学にとって、沢を歩くことと同様に、これらも必要であることは言うまでもありません。卒論の指導方法にも、多様なスタイルがあってしかるべきなのです。そして我々のところでは、希望者に、ある種のフィールドワークと実験・分析については、そのような基礎的トレーニングを提供する用意があります。
 <おわりに> <おわりに>
学部3年くらいの段階で、是非学生さんに希望するのは、それまでに受けた講義や実習など、限られた経験の中だけから研究室を選ばないでほしいということです。学部での授業は、研究内容の紹介ではありません。将来的に必要な基礎的な内容を系統的に身につけてもらうためのものです。授業の内容と教員の研究内容は異なるのが普通です。図書館などで勉強して、自分で自分の興味の在り処を探したり、教員の研究内容をよく調べたりする努力してください。地球物質科学科のような狭く深い教室構成には、早い段階で専門化できるという長所と、視野が広がりにくいという短所とが存在します。セミナーや学会などいろいろな機会を見つけて、教室内外の多くの研究者と積極的に交流していただきたいと思います。
修士では、フィールド・分析・実験にかかわらず、最初から完全な答えがわかっているようなテーマを出すことはありませんし、型どおりの議論でお茶を濁すことは認めませんから、本人が相応に頑張らないと、修士の学位を得ることはできません。
言うまでもないことですが,どのようなテーマ・手法を選ぶにせよ,学生諸氏はorder takerではなくself starterである必要があります.もちろん,テーマを相談して決めた時点で,こちらとしては一応のあらすじは考えますが,所詮,指導教官の浅知恵などロクなものではないと思ってください。教官自身の研究でも,真に重要な発見は,しばしば予期しなかった側面から為されるものです.教官は単なる道しるべに過ぎません。フィールドを歩き,化学分析を行い,あるいは実験を行った上で,もし行き詰まった時には,質問をしてもらえれば,一緒に考え,その時点で我々がベストと思うコメントを差し上げます。
 自分の研究の位置付けがわかるようになったら(ふつうM2・D1位),学科内外の院生や研究者と積極的に交流し視野を広げて下さい。また,新着文献のチェックを行うようにすると良いでしょう。目当てとしていた分野以外の論文に,貴重な発見があるかもしれません。もちろん世界の研究の根底に流れる動向を掴み,(国内ではあまり活発ではなくても)重要な分野を知るのに欠かせませんし,何より,不勉強な教官を偉いと思わなくなれる近道です(そうすればシメタもの。博士以上では,図書館の文献データベースによる検索を最大限利用しましょう。文献調査と論文読みは,しばしば目先の多くの作業に優先して重要になります.勉強(論文読み):作業(分析・実験等):論文書き の比率は,博士3年間を平均すれば1:1:1くらいになると思います。そうこうしているうちに,きっと日本人に限らず,自分の目標とする研究者が見つかるでしょう。その頃には,自分でうまく研究テーマを設定することもできるようになるでしょう。 自分の研究の位置付けがわかるようになったら(ふつうM2・D1位),学科内外の院生や研究者と積極的に交流し視野を広げて下さい。また,新着文献のチェックを行うようにすると良いでしょう。目当てとしていた分野以外の論文に,貴重な発見があるかもしれません。もちろん世界の研究の根底に流れる動向を掴み,(国内ではあまり活発ではなくても)重要な分野を知るのに欠かせませんし,何より,不勉強な教官を偉いと思わなくなれる近道です(そうすればシメタもの。博士以上では,図書館の文献データベースによる検索を最大限利用しましょう。文献調査と論文読みは,しばしば目先の多くの作業に優先して重要になります.勉強(論文読み):作業(分析・実験等):論文書き の比率は,博士3年間を平均すれば1:1:1くらいになると思います。そうこうしているうちに,きっと日本人に限らず,自分の目標とする研究者が見つかるでしょう。その頃には,自分でうまく研究テーマを設定することもできるようになるでしょう。
研究の縦糸と横糸(研究手法と研究対象)の両方を固定してしまうと,誰でも早晩行き詰まります。もしそうなったら,いずれかを軸として,新たに研究を展開してゆく努力が必要になります。積み上げのある,しっかりとした基礎を持つ研究テーマを選んでおくと,そのような時に比較的容易に隣の糸に乗り移れるかもしれません。
研究にあたっては,常に,なるべく大きな(重要な)テーマに取り組むことを心がけて下さい。何が重要であるか,必ずしも我々にも定かではありません。自分で考えてください。十年後に振り返ればわかるかもしれません。博士をとってスタートラインに立ったら,さらに一仕事一仕事,本質的なレベルアップを心がけてください。そうしたら,我々は研究者仲間が一人増えたことになり,より研究が楽しくなります。
最初にこのコラムを書いてから十数年が経ちました。この間、あまり加筆をする必要を感じて来なかった、つまり一定の価値観のもとに継続性のある大学教育を行ってこられたことは、ある意味、幸運なのかもしれないと感じられるこの頃です。
見せかけの指標はともかく、日本の経済は停滞して中間層の所得が減少し、政治情勢は混迷を深める一方、世界は絶えず激動しています。そんな中で、日本の大学だけが変わらずにいられる、変わらないで良い訳もありません。当然のように、この間の大学を取り巻く状況の変化は、その前の10年間以上に大きなものであったように思います。
リーディング大学院G-Safety
大きな変化の一つは、リーディング大学院や、来る卓越大学院構想の一部にみられるように、アカデミア以外への博士人材の輩出が強く大学に求められるようになったことです。これは日本の高等教育行政の主要課題の一つですが、一方で博士人材を十分に活かしきれていない受け入れ側にも問題があり一朝一夕に解決するとは思われません。地学専攻は、東北大で2件のみ採用された、博士課程リーディングプログラムの一つ、グローバル安全学トップリーダー育成プログラムに参画し、地球物理学専攻とともに「安全安心を知る」というユニットを構成してきました(私個人は、理学系の教務委員と後半のユニットリーダーを務めて来ました)。プログラムの内容はホームページ等を見ていただくとして、ここには、私がこのプログラムから学んだことを簡単に記します。
まず一つ目は、リーディングプログラムを志望するような学生諸君は、極めて柔軟であり、研究以外にも興味が広く、多様な能力があり志も高いということです。もちろん大学教員は、ほぼ研究者のみからなるmonotonousな集団ですから、学生の興味や志向の分布・重心とはズレていることは当然かもしれません。重要なことは、優れた研究能力に加えて、それ以外の高いポテンシャルを備えた学生が、少数ではありますが、確実に存在するということです。これまでの大学院教育では、たしかに、大学院生のごく限られた能力しか伸ばせていなかったと思います。大学は研究をするところなので、それで当然であるという見方もある一方で、これは大きな反省点であるというのが昨今の行政的な判断です。前向きに捉えれば、このようなプログラムによって、仮に少数であっても真に将来のリーダーたる人材が輩出できているとすれば、確かに素晴らしいことであると思います。
では、これまで我々は単に無為無策だったのでしょうか。なぜ偏屈に象牙の塔に籠っているようなイメージを持たれていたのでしょう(実際、その通り?)。おそらくその理由は、博士課程の間に経験すべき最も重要なこと
=ブレークスルーを、自分で掴み取ってもらうことに集中する必要があるから、だと思います。この傾向は、理学の博士では特に強いかもしれません。現在でも、この目的のために必要のない要素を大学院から排除することに躊躇しない理学の教員は少なくないと思います。このような傾向が正当化されるだけ、この「たった一つのこと」を会得するのは、やはり容易ではない。これが、私がリーディング大学院を通じて再認識したもう一つのことです。博士の学位を取得してから、アカデミア以外への進路が推奨される本プログラムの場合、研究内容と進路がよほどマッチしない限り、プログラム学生諸君の学位研究にとって「迷い」を生じさせる原因となりかねないのは事実です。退路を敢えて断たないで博士の研究を行うリーディングプログラムは、適性があり専門が適合した人には素晴らしいプログラムであり、そうではない場合には、なかなか難しいプログラムでもあります。このプログラムは、多くの専任教員や参画教員の先生方の努力によって成り立っています。このようなプログラムをなかなか受け入れられない、あるいは理解しようとしない教員が一部にいるのは、少々残念なことと感じます。しかし、個性・多様性が重要な研究者集団としては、それも致し方のないところかもしれません。GSの経験を踏まえ、より良いプログラムを目指して、ぜひ卓越大学院の採択へと繋げたいところです。
国際共同大学院(環境・地球科学)GP-EES
東北大学では、時代の要請に即した大学院改革を行う際、ディシプリンを堅持しつつ分野融合・境界領域の教育研究を行うため、既存の研究科組織を残したままを複数の研究科にまたがる(いわゆるアンブレラ型の)学位プログラム形式を採用しています。上記のリーディング大学院や、学際高等(旧国際高等)研究教育院などもその一つであり、卓越大学院も同形式での実施が想定されています。これらの学位プログラムは、授業料免除相当〜学振特別研究員DC相当のRA・奨励金等の経済サポートを伴います。これも詳しいことはホームページなどを参照していただくとして、簡単に言うと、東北大学が強みを持つ分野の一つである地球惑星科学・一部の環境科学の分野で、国際連携による大学院教育を行うというものです。本プログラムの研究室教育への影響は、たいへん大きなものがありますので、ここでやや詳しく説明しておくことにします。
2016年度から、JSPSからの受託事業である日独共同大学院プログラムがスタートしました。これは、JSPSに対応するドイツ研究振興会DFGのプログラムIRTG
(International Research Training Group)(実施機関はバイロイト大学バイロイト地球科学研究所BGI、教育組織としては数学・自然科学研究科実験地球科学専攻)と連携して、相互に学生や教員を派遣し、国際共同大学院を構成するというものです。詳しい経緯は省きますが、私はこの日独プログラムの日本側コーディネーターを務めています。多くの方のご尽力により、またいくつかの幸運が重なって、日独プログラムの開始から大きく遅れることなく、同年10月から環境・地球科学分野での国際共同大学院が、学位プログラム機構の当初予定より1年半、前倒しで開始されました。本国際共同大学院の特徴は、博士取得までの間に特定の協定校で原則6か月以上の博士研究を行い、国際共同審査を行うことにより、通常の博士(理学)の学位とプログラム修了の記載に加え、双方の大学から、Jointly
Supervised Degree(JSD)の証明をもらえることです。ダブルディグリーに準ずるものであり、学位に付加価値が付くことになります(このような意味で、スーパードクターと呼ばれることがあります)。
これまた多くの先生方のご尽力により、バイロイト大学・ハワイ大学はじめ、環境地球科学の様々な分野で世界をリードする多数の大学・研究科と、JSDの覚書(MOU)が締結されつつあります。今やほとんどの専門分野で、JSDのパートナーを見つけることができるはずです。国際的に活躍する研究者を育成するにあたり、その意義・効果は明らかでしょう。日本の地球惑星科学の大学院において、国際化や経済サポートの面で、おそらく先陣を切っていると思います。東北大の学生諸君には、是非このプログラムを存分に活用してもらいたいところです。バイロイト大のコーディネーターであるフロスト教授(私よりはるかに格上の世界的な研究者)と、冗談で、否、半ば本気で「自分がこのプログラムの学生になりたいよ」と、語り合うことがあります。自分たちの頃は良かった、というのではなく、自分たちが羨むような教育ができていることを誇りに思います。大学本部や文科省・JSPSのサポートに感謝したいと思います。またそれだけ、我々には責任も伴います。
博士後期課程(ドクターコース)への進学
博士研究員の就職難(いわゆるポスドク問題)は、我々の関連分野を見る限り、国立大学法人の定年年齢の延長と教員定員の削減が重なった最悪のタイミングは脱したように思われ、分野によっては(たとえば火山学のように)、団塊の世代の退職により、逆に博士人材の供給不足が始まっています。一方で、相変わらず常勤的な研究職への就職状況が厳しい分野もあるようです。重点化以降の博士後期課程定員が、純粋アカデミアのポジションに対しては多すぎるのは明白で、リーディング大学院等の経済サポートを伴う学位プログラムによるテコ入れを含めても、充足率は7割前後に留まっています。なお向上を目指す努力が強く求められているのが現状です。
学生諸君の博士後期課程への進学状況は、社会・経済情勢の影響を受けます。この十数年の間、長期的な経済の低迷に加えて数度の就職氷河期、地学関連業界での資源バブルとその崩壊などがありました。一度、厳しい就職状況を経験すると、学生諸君には、その記憶が長く引き継がれるようです。多少経済が好転したからといって、就職に対する見方が楽観されるわけではありません。当然のことでしょう。斯くして、彼らにとって博士後期課程への進学を躊躇させる要因は、増えることさえあれ、なかなか減ることはないのが現実です。様々な統計からみて、日本は博士人材の社会での活躍度に関しては後進国と言われています。少なくとも地球惑星科学の周辺では、その状況はあまり改善されているようには見えません。高度な専門性を備えた人材の不足は、中長期的に関連分野での国力の低下をもたらすことになるでしょう。いうまでもなく、有力大学の常勤教員ポストは最も重要で、いったんその分野の研究室が閉じてしまうと、人材の再生産自体が停止してしまいます。たとえば火山地質学・火山化学などの分野では、既に危機的な状況に陥っています。
2016年からの経団連関連企業の就職活動解禁時期の6月延期(2017年は4月になったようですが)は、案の定、実施側の意図に反して就活の実質的な前倒し(青田買い)を促進している面があるようです。これまで、最も落ち着いて研究を進めることができたM1の夏休みから、インターンシップという名の実質的な就職活動が始まり、その後、M2の6月頃まで、ほぼ丸1年間、就職活動が続くケースも見られるようになりました。研究生活のリハビリが済む前に夏休みに入ると、本格的にエンジンがかかるのは、予備発表が迫った秋口となります。本来2年間あったはずの博士前期課程が、今や、実質1年にも満たないというようなことにもなりかねません。さらには、就活としてのインターンシップは、学部4年の夏休みまで降りて来ているようです。
企業とのマッチングを確認したり、社会経験をしたりという、インターンシップ本来のポジティブな効果はもちろんあります。とても貴重な機会ですし、学生によっては、刺激を受けてさらに研究に身が入る場合もあるようです。しかしその分、学生諸君には、明確な目的意識をもって、就活産業から提供される大量の情報から自分に必要なもののみを主体的に取捨選択し、たとえ時間が細切れになっても、うまくつなぎ合わせて時間を有効に使うことが求められます。これは容易なことではありません。結果、修士修了時点での平均的な勉強量・仕事量、到達度は、右肩下がりの状況が続いています。経済的に自立するためのアルバイトの負荷が過大なケースもあります。もちろん、このような状況の大部分は学生の責任ではありません。彼らは、何と言われようが、自分の将来のためにしたたかに世を渡るしかないのです。
卒論・修論の指導方法どうする?
専攻全体でも留学生が増えていますが、特に我々のラボでは、幸いなことに、海外の熱心な留学生が多数、志望してくれるようになりました。アジア・ヨーロッパのトップレベルの大学を修了した諸君です。2018年4月から、留学生は5名となる(大学院生の約半数を構成する)予定で、このほかに、バイロイト大から6か月間、IRTG学生が2名(ドイツ・イタリア)、我々のラボで博士研究を実施しに来ることが決まっています。20倍を優に超える志願者から選抜された人たちです。東北大の日本人学生諸君も、学力ではそう引けを取らないはずなので、是非、彼らから良い刺激を受け、切磋琢磨してもらいたいと願っています。
研究室のセミナーや昼食会は、したがって、現在よりもさらに徹底して英語化することになります。プロの研究者を目指す博士後期課程の学生や、進学予定の修士の学生には、はじめのうち内容の理解度が低下することを差し引いても、良い環境になると思います。一方、日本人の卒論生や修士の学生には、それがプラスになるかどうかわかりません。おそらく彼らのセミナーは日本語で、場合によっては参加者を分けて、実施するのが現実的でしょう。ただしその場合でも、JpGUのようになるべくパネル(ppt)は英語、または日英表記としてもらいたいと思います。これは雑誌会でも同じことです。研究者の育成は、少数の日本人(自国)学生と、世界から集まる留学生に対して行う。欧米の大学では、これが当たり前ですので、この点でも、否応なくガラパゴス的環境から「グローバル化」しつつあるのかもしれません。
さて、卒論〜修論の指導では、英語の問題よりも、より本質的な問題が発生しているように見えます。以前は、研究室に配属した時点では、後期課程に進学するかどうか決まっていない(可能性がある)という人がかなりいて、また途中で就職から進学へと進路変更するケースも少なくありませんでした。しかし最近では、最初から博士後期課程への進学を標榜する学生以外が、途中で気が変わって進学することになるケースはほとんど見られなくなりました。しかし本来、研究の面白さに気づいたり、自分が研究に向いているかどうかの適性を判断できるようになったりするには、M1を終えるくらいまでの時間が必要なのではないでしょうか。なぜこうなってしまったのか。根底に、博士離れという世相の変化があるのは間違いないでしょう。「失われた20年」の間に、気分的にも社会全体にゆとりが無くなりました。免許や資格のある職業を選んだり、少しでも早く定職に就いてリスクを減らそうという傾向が強まったりするのは当然のことでしょう。また、就活開始の早期化・期間の長期化によって、研究に集中する時間を取れなくなり、研究の魅力に気づく機会を失していることも一因になっているように見受けられます。繰り返しになりますが、これは基本的には、学生の側に原因があるわけではありません。進路についてどこまで考える時間を持てるかという問題は、常に周囲の環境要因に依存しますので、許される範囲で判断するしかないのが世の常です。しかし、もし研究職についての適性を判断するのに必要最低限の研究期間がとれていないとしたら、大学としてはやはり憂慮すべき事態です。
このような状況では、ある程度「型」にはまった研究、大きなプロジェクトの一部などの方が学生本人にとっては楽でしょうし、それなりに使える結果も出やすいと思います。指導する学生の人数が増えてしまうと、実際問題としてそうせざるを得なくなるという面もあります。しかし、やはり一部でも、チャレンジングなテーマに果敢に取り組む人がいてほしいと思います。学生諸君の研究テーマを策定するときには、どうしたら潜在能力を引き出せるだろうか、ひょっとしたら大化けするかもしれない、とでも考えなければ、やっていられません。そうでなければ、昔のように放任にして、自分は自分として研究をしていた方がずっと楽しく生産的でしょう。なので、おそらくもうしばらくの間は(夏休みに伽藍とした大学で頭を抱えつつも)今までのやり方を踏襲することになりそうです。その結果、修士論文がうまくまとまらなくても、それは一向に構わないと思うのです。
研究分野
岩石学・火山学
固液共存系の物理化学
基礎となる学問体系
化学熱力学・相平衡岩石学
微量元素・同位体の地球化学(主に元素分配論に基づくシステマティクス)
混相系(鉱物・マグマ・フィールド)のレオロジー
移動速度論・化学反応速度論
多結晶体の材料科学
地質調査法
野外地質調査,帯磁率計・地理情報システム(GIS)の活用
岩石記載/局所分析
偏光顕微鏡
微分干渉顕微観察
レーザー共焦点顕微鏡観察
高分解能観察(FE-SEM, TEM)
EPMA(WDS・EDS)
EBSD
カソードルミネッセンス
高温その場FE-SEM観察・EDS分析
Micro FT-IR
ラマン分光
LA-ICPM, SIMS
岩石組織解析(結晶サイズ分布など)
全岩化学分析
湿式定量分析
安定同位体分析
主要・微量元素分析(XRF・ICP−MS)
Crygenic法, カールフィッシャー滴定法
X線CT(inhouse/放射光)
高温高圧実験法
試薬合成法, 大気圧電気炉
石英ガラス管法
集光炉・集光変形実験装置
外熱式ガス圧装置(水熱実験)
TZM, 開放セル, 減圧率制御
マグマ・岩石の変形溶融観察実験
マグマ粘性・レオロジー測定
ピストンシリンダー型装置による高温高圧実験
これらにおける酸素分圧制御(ガス混合・固体緩衝)
|